「KINTSUGI KIT」解説書の和訳付き
ある日、愛用していた茶碗の縁が欠けてしまいました。
特別高価なものではなく、無名の作家さんの作品。
でも手に馴染み、毎日のように使っていたので、「もう一度使えるようにしたい!」と思い、金継ぎについて色々調べ始めました。
ところが、本格的な金継ぎセットはなかなかのお値段。
正直、この茶碗なら2つ買えてしまうくらいの金額で、ちょっと手が出ません…。
迷っていたところ、Amazonで見つけたのが今回の「金継ぎセット」。
なんと 2,149円という安さ!
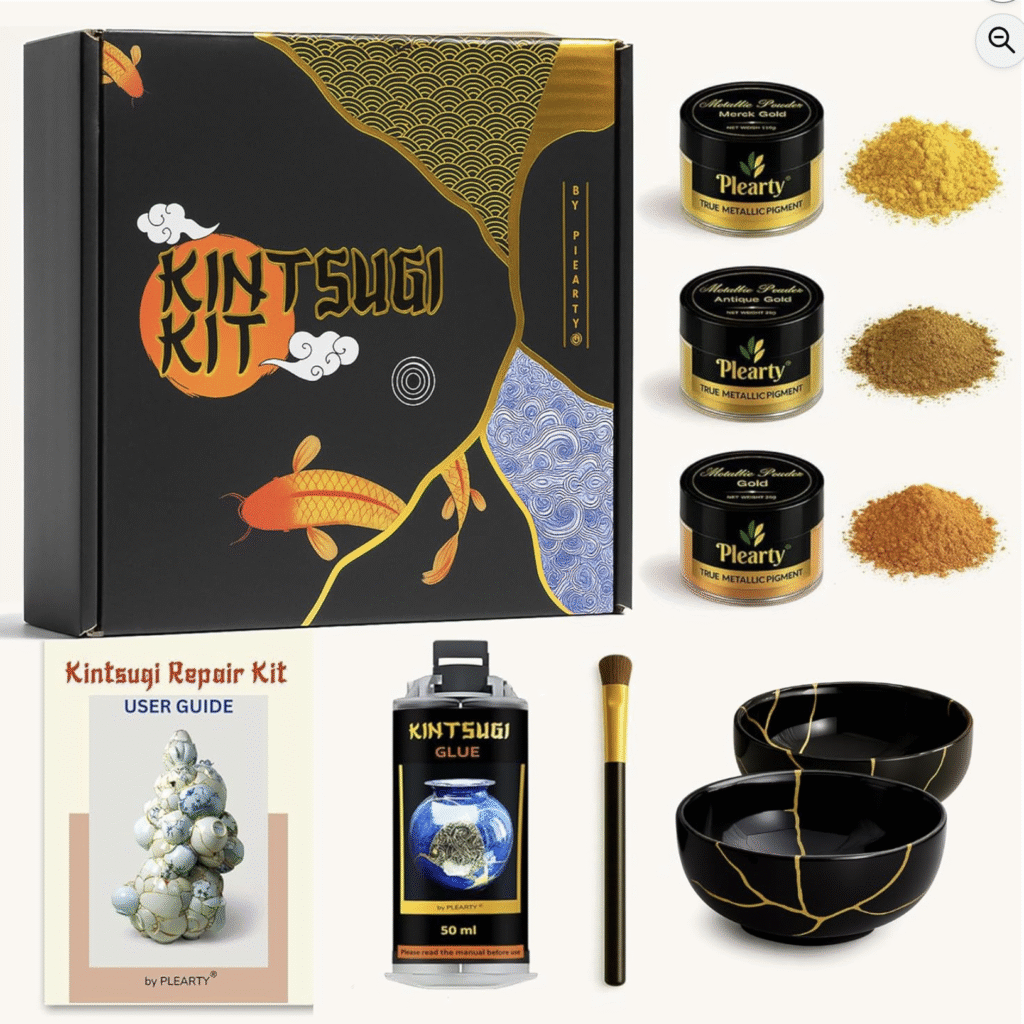
「どうせ中国製かな」と思ったら、意外にもドイツ製。
お手頃価格に惹かれて試してみることにしました。
どうせならと、欠けていたほかのお皿や茶碗もまとめて挑戦!
その結果がこちらです。

まず最初に伝えたいこと
このセット、正確には 「金継ぎセット」ではなく「金継ぎ風修復セット」 です。
違いはシンプルで、漆ではなく 接着剤に金粉を混ぜて使う という点。
だから本格的に金継ぎを学びたい人には向きません。
ただ「お気に入りをなんとか蘇らせたい」「金継ぎ風の雰囲気を楽しみたい」という人にはアリだと思います。
ただ、このセットの問題は、解説書が英文しかないところ。
なので、あなたのために解説書の翻訳PDFを以下にアップしました。
同梱リーフレット前半部分の翻訳1(安全上の注意や使用上の心得が書かれています)
同梱リーフレット後半部分の翻訳2(クイックガイド:実際のハウツー部分です)
これで完璧!かと言うと、、実はこの解説書とても立派な「金継ぎの意義」などが書いてあるのですが、肝心の使い方がいまいち分かり難い。
なので実際にこのセットを使う際には、解説書だけではなく、以下を読んでからご使用ください。きっと「読んでよかった」と思われるはずです。
使ってみてわかったコツと注意点
① パテは接着用じゃない
このセットのエポキシパテは接着力が弱め。
割れを繋ぐのではなく、欠けた部分を埋めるため に使います。
見た目はグレー(黒と白を混ぜると灰色になる)なので、最後に接着剤+金粉でカバーする必要があります。
欠損部分をこのようにパテで補えます
② 接着剤はちょっと癖あり
- すぐ固まる
接着剤は二液が混ざると一気に固まるので、出したらすぐ作業を!
先端ノズルはすぐ詰まるので、ピンで塞ぐなど工夫が必要だと思います。
私はそれを怠ったばかりに、一発で使えなくなりました!


この様に帽子を脱がせて、ノズルを付けて、お尻からところてん方式で押し出します
- 少しずつ塗る
はみ出すとそのまま固まり、見た目が汚くなります。必要最小限を慎重に。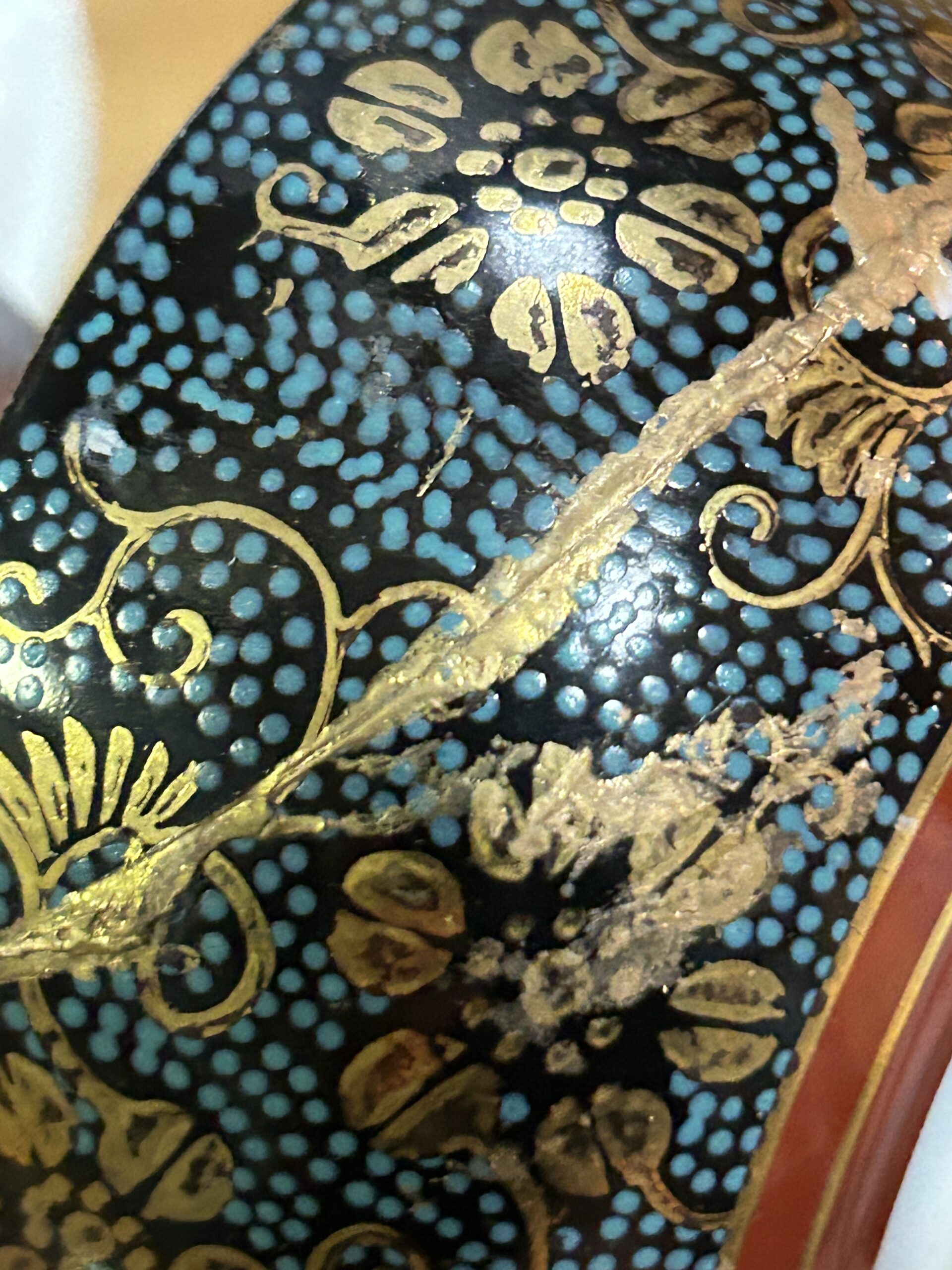
失敗例:はみ出しすぎです。 - 濡れ雑巾は必須
はみ出した接着剤は、固まる前ならすぐ拭き取れます。
パテも黒いので、指で触れると跡が残りますが、それも固まる前なら拭き取ればOK。
(ただ、上記のような柄がある物だと拭き取っても綺麗に取れません) - 筆は接着剤に使わない!
筆で接着剤を塗るとすぐに固まって使えなくなります。
接着剤はノズルから直接か、木のヘラを使って塗布します。
筆は金粉を振りかける専用 と覚えてください。 - 一度に繋がない
割れたパーツは一つずつ接着。焦ると接着剤が固まってしまい、次のパーツに使えなくなります。
ひとつのパートを繋いで、また次へ、、 - 金粉はほんの少しでOK
米粒くらいでも十分発色します。入れすぎると接着力が落ちるので注意。
③ スパチュラ(木のヘラ)で仕上げない
木のヘラで表面を整えるとザラザラになります。

代わりに「まずは接着剤だけで表面を覆い、接着剤が自分で平らに広がるのを少し待ってから、その上に金粉を振りかける」と、以下のような自然にきれいな仕上がり(本来の金継ぎ風ではないけれど)になります。

厚みは出ますが、この方法がいちばん安定していました。
④ 付属の小さな陶器は練習用
これらの器は溶剤を混ぜるものではなく、どうやら「練習用」みたいです。
箱に2X Beautiful ceramics for practiceと書いてあります。
いきなり本番に挑まず、まずはここで試すのがおすすめです。
一度割って、繋いでみるものいいかもしれません。
まとめ
仕上がりは本格的な金継ぎに比べると少し厚ぼったいですが、
「欠けて使えなくなった器がもう一度使える」というだけで大満足。
本物の金継ぎとは違いますが、気軽にトライできるので、
「大切にしている器をもう一度使いたい」という方にはおすすめできます。
不器用な私でもなんとかできたので、きっとあなたならもっと上手に仕上げられるはず。
ぜひ挑戦してみてください。



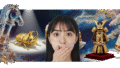
コメント